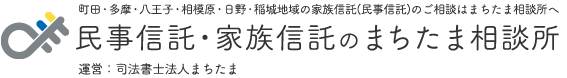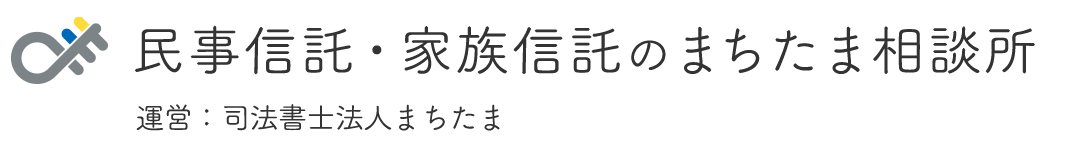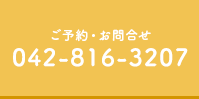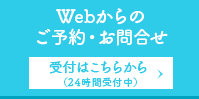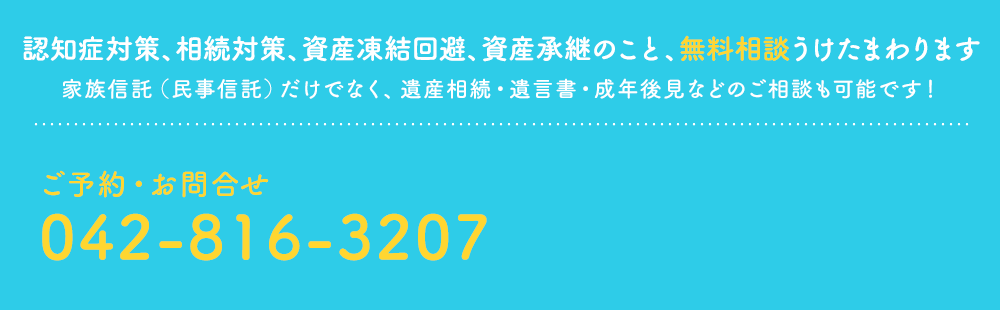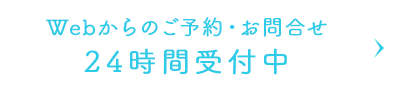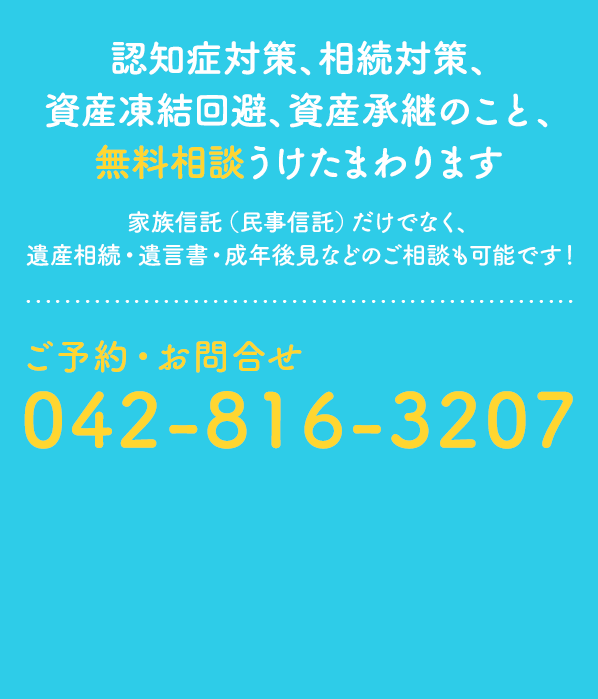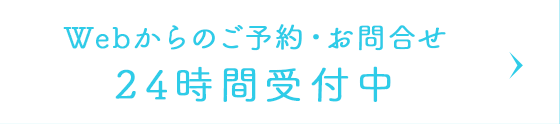信託Q&A

- 追加信託とは?

民事信託(家族信託)では、信託がスタートした後に、信託財産に追加して財産を組み入れたいということがあります。
例えば、家族信託をスタートさせる段階では、現金100万円を信託財産として設定していたけれど、信託が始まってから追加で現金や不動産を追加で信託するような場合です。
これは「追加信託」と呼ばれることが多いですが法律用語ではありません。
また、この既存の信託に追加で財産を支出する追加信託に関しては、法的構成が明らかにされておらず(※)、実務上の概念として使用されています。※「新たな信託設定と信託の併合」という学説や「信託の変更」という学説など。
通常の家族信託では追加信託をすることはそれほど多くはないかと思われますが、信託契約書には追加で信託ができるように追加信託の条項を定めておくことは珍しくありません。
なお、追加信託という抽象的な概念を利用して信託を組成してしまうことに否定的な見解もあり、追加信託の条項を安易に設けることは避けるべきという意見もあります。
追加信託の方法委託者は、受託者の書面による同意を得て、 本信託の目的の達成のために、金銭を追加信託することができる。
信託契約書に定める追加信託の条項としては上記のような例が挙げられます。
追加信託は先ほど申し上げましたとおり、実務上の概念に過ぎないので、その成立要件を信託契約書でどのように定めるかがポイントになります。
原則として「委託者と受託者の合意」を追加信託の成立要件をとすることが通常です。
しかし、中には「委託者の一方的な行為」によって追加信託を可能にしている信託契約書もあるようです。
例えば、「委託者が受託者の口座に送金することで追加信託が成立したものとみなす」というような条項です。
このような場合には受託者の合意なく追加信託が可能になりますので、受託者の知らない内に信託財産が増加し、受託者の責任が重くなってしまう可能性があります。
また、信託事務遂行上、管理者である受託者の知らない間に信託財産が増えてしまうと、受託者が信託財産を適切に管理するができなくなります。法的構成が明確になっていない追加信託だからこそ、その成立要件をしっかりと信託契約書に定めておくことが、後々のトラブルを回避することにも繋がりますので、「委託者と受託者の合意」を追加信託の成立要件にすることは最低限必要ではないかと思います。
関連Q&A
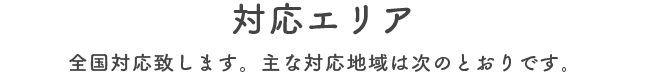
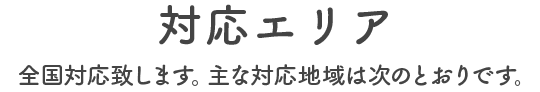
- 東京都
町田市、八王子市、多摩市、稲城市、立川市、府中市、狛江市、調布市、日野市、昭島市、福生市、武蔵村山市、青梅市、あきる野市、羽村市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、国立市、国分寺市、小金井市、小平市、東大和市、東久留米市、東村山市、その他23区全域 - 神奈川県
相模原市(緑区、中央区、南区)、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横浜市、川崎市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 - その他関東近郊(山梨県、埼玉県、千葉県 他)